ラジオのちから②
- 清水碧
- 2022年6月23日
- 読了時間: 4分
前回に引き続き、韓国のラジオの話です。今日はラジオを聞くことで学習面でも精神面でも助けられている話について書きます。
まずは学習面です。多くの人が想像できるであろう、リスニング力の向上という点についてはその通りであるため、ここでは省略します。
ラジオを聞いていてリスニング力の次に伸びたのはやはり語彙力です。いろいろな立場のいろいろな人からメッセージがくるため、単語帳や教科書には載っていない単語や、載っていても自分で学習する際にはなかなか覚えられない、生活の中での単語が身につきます。
例えば「就活をしている人」のことを“취준생(취업 준비생)”と言うんだな、高校生などが授業が終わった後に勉強する時間を“야자(야간 자율 학습)”と言うんだな、それから離乳食を作っているお母さんからのメッセージを聞いて、離乳食はそのまま“이유식”と言うんだな、などです。
最近流行っていることばもたくさん知ることができます。とは言っても、いわゆるスラングというよりはことばの変化を知ることができるというのが正しいかもしれません。
例えば、私が学部で韓国語を学んでいた頃は、語尾の“-아/어서”の前には “-았/었-”や“-겠-”はこないとされていましたが、ラジオを聞いていると今はかなり普通にくるということが分かります。
それから、ラジオを何年か聞いていて自分でこの能力が伸びていると気づいたのは、韓国の人の名前を覚えやすくなったということです。それもそのはず、2時間のラジオの中で、著名人からメッセージを送った一般の人の名前まで何十人もの名前を毎日聞くことになるので、こういう名前のパターンはよくある、あるいはこういうパターンはあまりないというのが無意識に分かるようになっていました。これはとても嬉しい効果でした。
また、ラジオでは今流行っている曲だけでなく、いろいろな時代の曲が流れるので、昔流行った曲や歌手を知ることができます。これも韓国の人と話す時に役に立っているので、学習面の効果の1つと言えるかもしれません。
私のように放送翌日にPodcastでラジオを聞く場合は著作権の関係で曲はカットされてしまうのですが、前奏だけ少し流れたり、DJによる曲の説明や感想、リスナーからの反応などを聞いて気になった曲をYou Tubeで聞くことがあります。そうしていると過去の有名な曲も自然に覚えていたりします。
次に精神面で助けられている点についてです。これは“푸른밤”を聞いていて、最初の頃によく“라디오만 한 친구가 없다”という言葉をDJが言っていて、最初はあまり分からなかったのですが、それを身をもって実感するようになりました。
というのも、だんだんと年齢を重ねてくると、昔のようにいつでも気楽に友達に連絡するのが難しいなあと思うときがあるためです。それぞれ仕事や家のことなど、状況が違ったり事情があったりして忙しく、いきなり連絡したら悪いかなと思うときがあります。昔は用事がなくても連絡していたけれど、そういうのは良くないのかなと思ったり...
それでも誰かと話したいなとか、自分の思っていることを言いたいなと思ったときに、これはmini(生放送を聞く際に使うアプリ)を使うようになって分かったのですが、ラジオに言えば良いのです。
もちろん友達に言うようなことを全て書けるわけではありませんが、時には友達には言わないどうでも良いことを言っていたりします。自分の他にも自分と同じような状況の人たちがいて、運がよければ放送で読んでもらえる、それは思っている以上に力になります。
ラジオは24時間流れているので、普段自分が聞くラジオでなくても、眠れなかったらラジオ聞こう~という、実際にそうしなくてもそういう選択肢があると思うとそれだけで気楽になったりします。
ですので、“라디오만 한 친구가 없다”ということばは本当だなと思うことが多く、私を支えてくれるものの1つになっています。
この記事ではラジオを聞くことによる学習面と精神面の効果について書きましたが、これは結果的に得ているもので、目的としていたわけではありませんでした。あまり大きな趣味のない私ですが、強いて言うなら韓国のラジオを聞くことが細々とした趣味なのかもしれません^^

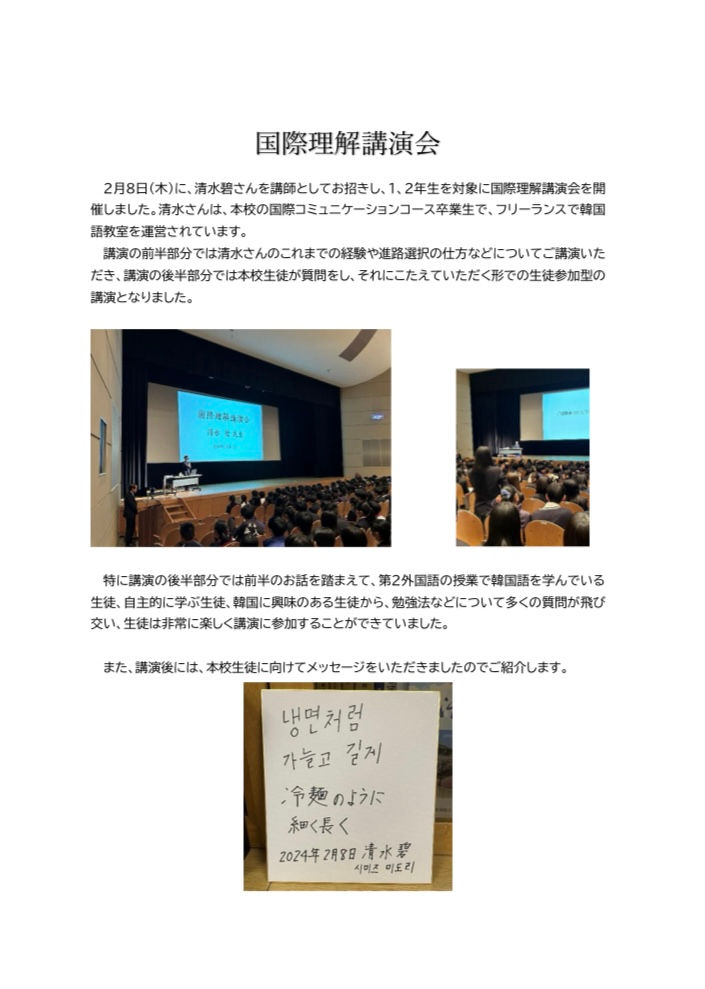


コメント